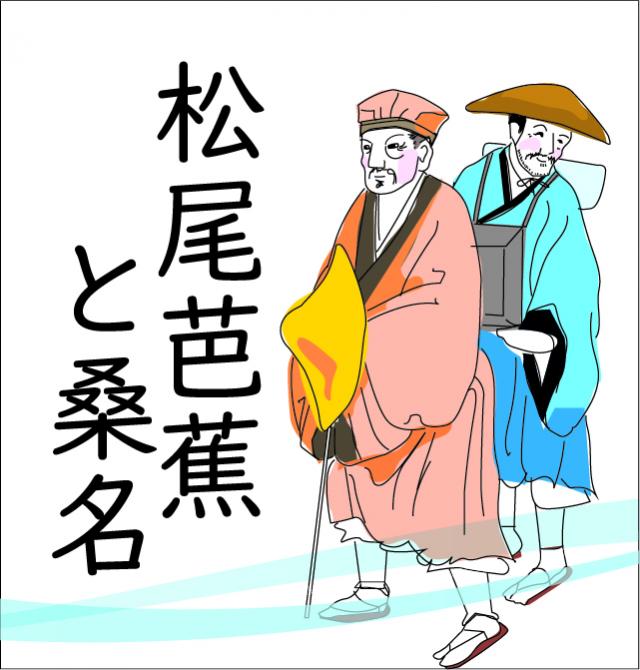ここから本文です。
旅に生き、各地を訪れる中で名句を残した俳人・松尾芭蕉。伊賀上野出身。桑名にも何度か訪れ地元の文化人たちと交流しています。また、弟子の河合曽良は長島出身で、名前の由来は木曽三川の木曽川と長良川からとった、という説もあります。桑名とゆかりの深い芭蕉の足跡をご紹介します。
※この特集ページは2007年に発行された「桑名ふるさと検定桑名のいろは」の「松尾芭蕉と桑名」を再編集したものです。
目次
『野ざらし紀行』の旅
芭蕉(注1)は生涯に多くの旅をしていますが、桑名を通ったのは、彼の句集によると3回です。
芭蕉は、貞享元年(1684)10月、自分と同じ北村季吟門の俳人で、大垣で廻船問屋を営む豪商谷木因とともに揖斐川を下って桑名を訪れ、本統寺を訪ねています。この時、本統寺の住職を勤めていたのは、やはり北村季吟の門人であった琢恵(俳号古益)でした。
桑名から熱田へ渡り、12月には伊賀へ戻って正月を過ごし、翌年の3月に再び本統寺を訪ねて3日間滞在しています。この時の旅を題材に刊行された本のタイトルをとって『野ざらし紀行』の旅と言います。
桑名で芭蕉が詠んだ句は次の通りです。
《多度にて(多度大社)》
■宮人よわが名をちらせ落葉川(注2)

多度山から見下ろす木曽三川と伊勢湾

多度大社

多度大社 芭蕉句碑
《桑名にて(本統寺、浜地蔵)》
■冬牡丹千鳥よ雪のほととぎす(注3)
■明ぼのやしら魚白き事一寸(注4)
《桑名から熱田までの海上にて》
■遊び来ぬ鰒(ふぐ)釣りかねて七里まで(注5)
■鰒釣らん李陵七里の浪の雪(注6)

本統寺 芭蕉句碑

浜地蔵 白魚句碑
芭蕉句碑所在地
| 多度大社 | 住所:桑名市多度町多度1681 TEL:0594-48-2037 時間:8時30分から17時00分 駐車場:100台 |
|---|---|
| 桑名別院本統寺 | 住所:桑名市北寺町47番地 TEL:0594-22-0652 駐車場:12台 |
| 浜地蔵(龍福寺) | 住所:桑名市小貝須浜 |
『奥の細道』の旅
貞享4年(1687)10月江戸を出発し、熱田・桑名を経て伊賀へ帰郷した旅は『笈の小文』と呼ばれていますが、桑名で詠まれた句はありません。
元禄2年(1689)年3月から9月までの『奥の細道』の旅は有名で、大垣が終点とされています。
その後芭蕉は9月6日、同行者河合曾良(注7)の叔父が長島の大智院の住職であることから、大垣から揖斐川へ下って、長島に泊まり、伊勢神宮の遷宮を見るため、二見に向かっています。このため、『奥の細道』の最後の句は、川を下る船に乗る時の別れの句となっています。
■蛤のふたみにわかれ行く秋ぞ(注8)
大智院へは3泊して次の句を詠んでいます。
■憂きわれを寂しがらせよ秋の寺(注9)

長島から多度山をのぞむ

大智院

長島増山家六代藩主正賢自筆による「蕉翁信宿処」

大智院 芭蕉句碑
芭蕉句碑所在地
| 大智院 | 住所:桑名市長島町西外面1219番地 TEL:0594-42-1589 近鉄長島駅より徒歩約17分 |
|---|
注釈
(注1)…松尾芭蕉(1644~1694)
芭蕉は伊賀上野(現在の三重県伊賀上野市)に生まれ、本名は松尾宗房と言いました。上野城代藤堂家に仕え、俳句を京都の北村季吟に学んでいました。このころの俳号は「伊賀上野宗房」で寛文12年(1672)、29歳の時江戸へ出て本格的に俳諧師となりました。延宝3年(1975)に「桃青」を、天和2年(1682)に「芭蕉」の俳号を名乗っています。
(注2) …宮人よわが名をちらせ落葉川
落葉川は、多度大社の一の鳥居の前の川のことです。初句では「宮守よわが名を散らせ木葉川」となっています。この句は木因の「伊勢人(いせびと)の発句(ほっく)すくはん落葉川」(掬うと救うをかけて、伊勢の古い俳諧を救って一新してやろう)の句を受けて、まぜ返した句となっています。意味は「多度大社の宮司よ、今神社に落書きされたわたしの名前を、落葉と一緒に川にまき散らせてほしいものです。」
(注3)… 冬牡丹千鳥よ雪のほととぎす
冬牡丹から初夏の牡丹とほととぎすを連想し、千鳥をほととぎすになぞらえています。「雪の中のほととぎす」はありえない物のたとえで、本統寺の珍しい冬牡丹をたたえたもので、亭主(本統寺住職)への挨拶としています。「雪の庭に珍しい冬牡丹が見事に咲いています。海辺から飛んでくる千鳥はほととぎすのように思われます。」
(注4)…明ぼのやしら魚白き事一寸
白魚は春の季語ですが「一寸」(幼魚)としたことで冬の季語としています。「夜が白々と明けていく浜辺で一寸ばかりの小さな白魚を掬ってみました。その白さが目にしみました。」
(注5)…遊び来ぬ鰒(ふぐ)釣りかねて七里まで
「七里」は桑名から熱田宮までの海上の距離で、この間の渡しを通称「七里の渡」と言いました。「海上の船遊びにふぐ釣りをしたが、少しも釣れないうちに七里も来て、熱田へ着いてしまいました。」
(注6)鰒釣らん李陵七里の浪の雪
李陵(~紀元前74年)は中国前漢時代の武将ですが、引退後七里灘で釣りをして過ごしたという伝説から「七里灘と名が同じ七里の渡で、雪にまみれてふぐ釣りを楽しもう」の意味です。また、李陵は、後漢時代の人でやはり七里灘で釣りをして世を送った「子陵」の間違いだという説もあります。
(注7)…河合曾良(1649~1710)
曾良は信濃国下桑原村(現在の長野県諏訪市)に生まれましたが、父母・養父母とも亡くなり、長島の親戚に引き取られ、一時長島藩主松平良尚に仕えました。後江戸へ出て俳諧を学び、芭蕉の『奥の細道』に同行しました。
(注8)…蛤のふたみにわかれ行く秋ぞ
『奥の細道』最後の句です。伊勢国桑名の名産蛤の蓋と身を伊勢の二見(ふたみ)にかけ、さらに「別れて行く」から「行く秋」を引き出している技巧的な句として有名です。「見送っていただいた親しい人たちと蛤の蓋と身を引きはがすようなつらい別れをして、私は深まっていく秋とともに、伊勢の二見への旅に出ます」
(注9)…憂きわれを寂しがらせよ秋の寺
「晩秋の寺には心にしみ通るような寂しさがただよっています。心に憂いをいだく私は、この寂しさの中で、さらに深い境地に達したいと思います。」呼びかけは情感を深める手法と言われています。
特集 くわなの過ごしかた。
掲載日:2025年4月21日
トップページ > 特集 くわなの過ごしかた。 > 松尾芭蕉と桑名